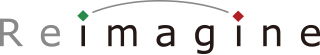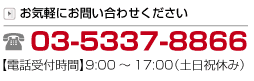地方公務員の遺族補償年金支給 男女差は違憲
大阪地裁は25日、遺族年金の補償支給条件を男女で区別している地方公務員災害補償法(地公災法)の規定について、違憲と判断した。
原告には妻がいたが、勤務先の中学校での校内暴力などで97年にうつ病を発症し、原告が51歳だった98年に自殺した。その後2010年に、「公務災害」と認められ、原告は2010年に遺族年金の支給を求めた。しかし、支給対象は地公災法に「夫を亡くした妻」か「妻の死亡時に55歳以上の夫」とあるため、対象者でないとして、地方公務員災害補償基金から遺族年金の支給を拒否された。そこで原告は「男女で受給資格を分ける」同法は、憲法14条の法の下の平等に反するとして、不支給の決定の取消しを求めていた。
判決は、地方公災法が「遺族補償年金の支給条件」を男女で区別していることについて、法律制定当時には「専業主婦」が一般的な家庭モデルであり合理性があったものの、女性が社会進出し「共働き」世帯が一般化してきたことや男性の非正規雇用が増加していることなどを踏まえ、現在では「配偶者の性別により、受給権の有無が異なるような取扱いは、差別的で違憲」であると判断した。
同様の男女区別の規定は、民間の労災保険や厚生年金などにも存在する。
今後、これらの規定についても合理性を問われる可能性がある。
http://www.asahi.com/articles/OSK201311250021.html